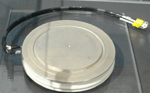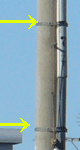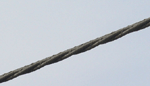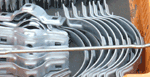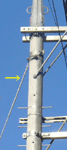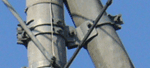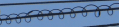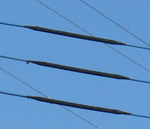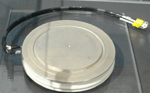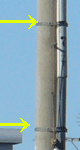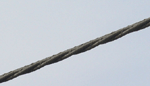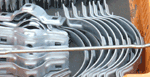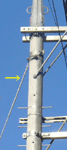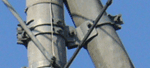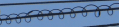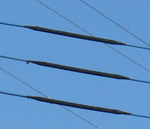|

電柱装柱用語一覧(さ〜そ)
●サイリスタ
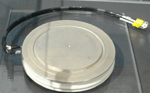
電極の+をオンオフして大電流を制御する半導体。
●差込式引留金具(さしこみしきひきどめかなぐ)

引き留めに使う金具。吊架線の末端部を差し込むことによって接続する。
●サドル
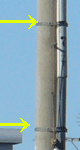
電線管を電柱に取り付ける金具。
●三相交流(さんそうこうりゅう)
周波数が同一で、
各位相が120°ずつずれたサイン(正弦)カーブの交流。
●三相交流三線式(さんそうこうりゅうさんせんしき)
三相交流を三本の電線で送る方式。
●三相交流四線式(さんそうこうりゅうよんせんしき)
三相交流を四本の電線で送る方式。
三相交流三線式に中性線を増やしたもの。
工場などに使われるらしいが、
高圧線ではあまり見かけない。
●CATV線
ケーブルテレビの線。
●CV

ビニル絶縁ビニルシースケーブル。
3本の導体(電気が流れる線)をそれぞれ架橋ポリエチレン絶縁体で覆い、
それをまとめてビニルシースでまとめた電線。
●CVT
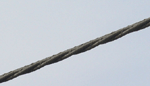
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。
3本それぞれの導体を架橋ポリエチレン絶縁体で覆い、
更にその外側をビニルシースで覆った電線。
3本は捻り合わせる(電線用語では「撚る」と言う)。
高圧線を地中に引き込む時に使われるが、
東京電力では都市型配電線の高圧線にも使われる。
●自在バンド(じざいばんど)
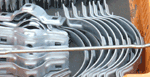
電柱に街灯や電線管、CVTなどのケーブルを取り付けるためのバンド。
●支持点繰上げポール(しじてんくりあげぽーる)
引き込み線などの電線の支持を、
構造物より上空でする場合に使うポール。
●支持物(しじぶつ)
電線を支持する電柱のこと。
●ジスコン
ディスコンとも言う。断路器のこと。
●ジスコンフック棒
断路器を開閉するときに使う棒。
●支線(しせん)
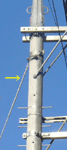
電線の終点などで、一方に偏った張力が加わる場合、
その張力に耐えるために反対側斜め下や横にかける線。
支線に電気が流れないよう、
途中に玉碍子や井型碍子を挟む。
●支線ガード(しせんがーど)

支線の地面方向に取り付ける塩化ビニル製の筒状のもの。
支線抜き取り防止や、支線に人が足を絡めないようにするためにある。
人や車に気付くよう警戒色(黄色)の場合が多い。
●支線バンド(しせんばんど)

支線を電柱に取り付ける際に使う、金属製のバンド。
●支柱(しちゅう)

一方に偏った張力が加わる場合、
その張力に耐えるために本柱に対して斜めかける電柱。
●支柱金具(しちゅうかなぐ)
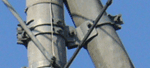
支柱と本柱を接続する金具。
●遮断機(しゃだんき)
異常時などに安全に電気を遮断できる器具。
●遮へい線(しゃへいせん)

電線から漏電した電気(コロナ放電など)が人や植物、
他の電線などに当たらないように設けた保護線。
通信線の通信障害防止のためにも取り付けられる。
●ジャンパー線

耐張碍子同士を結ぶ電線。
●充電(じゅうでん)
1、コンデンサや蓄電池などに電気を流して蓄えさせること。蓄電。
2、電線などの導体や配送電機器が帯電している状態のこと。
充電中は危険なので安全距離から内側に近付いてはいけない。
●周波数(しゅうはすう)
単位時間に同じことを繰り返す回数。
交流の場合、0〜+の最大値〜0〜−の最大値〜0を1回とカウントし、
1秒間にそれが何回行なわれたかを数える。
単位はヘルツで、
富士川を境に東は50ヘルツ西は60ヘルツになっている。
●シンプル吊架金物(シンプルちょうかかなもの)

複数の方向から吊架線が来ている場合、
それらをつなぐ輪状の金物。
●スパイラルハンガー
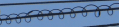
従来のケーブルハンガーに変えて、
吊架線と電線を結びつけるらせん状の線。
ケーブルハンガーのように1個1個取り付けなくて済むので、
電線工事の時間が短縮できる。
●スペーサ

(通常型)

(十字スペーサ)
電線の間隔を保持するために取り付ける器具。
これをつけると風による電線同士の接触などが防げる。
代表的なのに十字スペーサなどがある。
●スポットネットワーク受電
同一の変電所から多数の回線で受電すること。
1回線が使えなくなったときも他の回線で代用出来る。
●スリーブ

電線接続に使う、管型の軟銅。はんだ付け不要。
●スリーブカバー
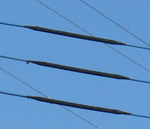
スリーブに被せる絶縁カバー。スリーブの形状に合わせて様々な形がある。
●スリップオン碍子

碍子から直接変圧器に接続できる碍子。
配線がコンパクトになり、見た目が良くなる。
東京電力の環境化配電線装柱に見られる。
●整流器(せいりゅうき)
交流を直流に変換する装置。
●責任分界点(せきにんぶんかいてん)
電力会社支店や支社同士、電力会社同士、
または電力会社と需要家の管理責任の境目。
大抵、開閉器か計器用変圧変流器を境にする。
●絶縁カバー(ぜつえんかばー)

電気工事の際、碍子やカットアウトなどに取り付け、
万が一電気が流れた際、作業員を感電から護る防具。
●絶縁油(ぜつえんゆ)
変圧器や地中電線の絶縁に使う粘度の低い油。
●接続線(せつぞくせん)

交差する二つの配電線を接続する線。
●接続端子函(せつぞくたんしかん)

電話線を分岐する時に使う箱状の機器。
●セパレータ

電線同士が接触しないよう間に挟む金具。
スペーサと異なり碍子は無いので、電話線やCATV線に使う。
●装柱(そうちゅう)
電柱に腕金やアースなど配電線の器具を取り付けること。
電柱装柱用語一覧(た〜ち)へ
電柱装柱資料館へ戻る
川柳五七の電線のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|